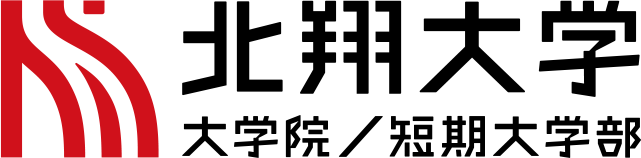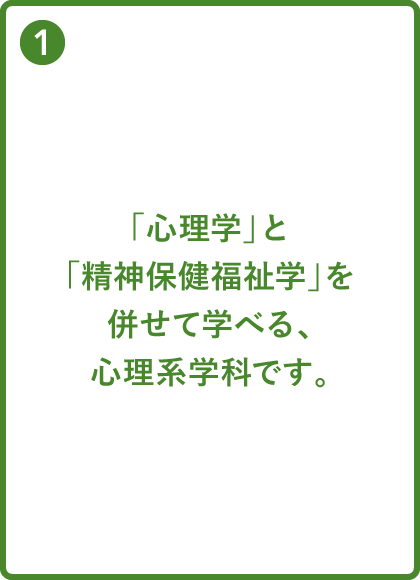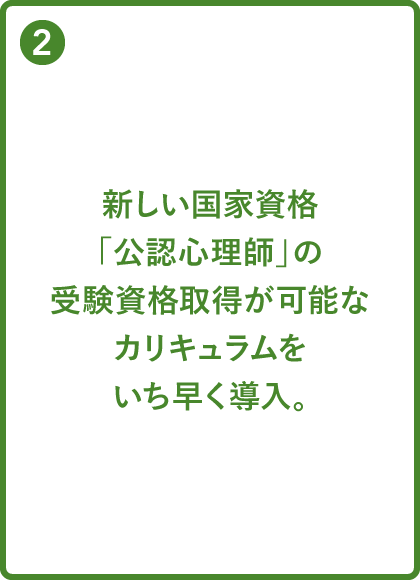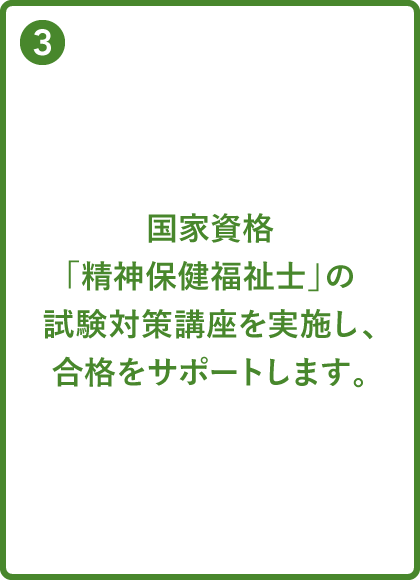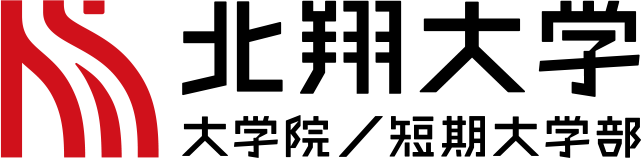心理カウンセリング学科
心理カウンセリング学科の3つの強み
>学科独自ブログはこちら
心理カウンセリング学科の2つの領域

心理学領域
「人の幸せ」のために、カウンセリングやセラピーを行い、心理検査などを通してこころの状態を知る。それが、多種多様な「心理学」に共通する大きな目的です。いま、どのような心理学に興味がありますか? そして、どのような人々の幸せに役立ちたいですか?あなた自身のこころを見つめてみてください。

精神保健福祉学領域
「人の幸せ」のためには、その人自身への働きかけだけでは立ち行かないケースが往々にしてあります。精神保健福祉学とは、こころに困りごとを抱えるご本人やご家族の生活をまもるために、関連する諸制度などを活用し、多職種と連携しながら支援する方法を学ぶ学問領域です。その人らしい暮らしを実現する道しるべとして、病院や学校、福祉施設などで卒業生が活躍しています。
3つのポリシー
-
1
DIPLOMA POLICY
学位授与方針
本学科では、以下に示す資質・能力等を修得した者に学位を授与します。
【知識・理解】
(1) 豊かな人間性と社会人としての幅広い教養を身に付けている。
(2) 心理学及び精神保健福祉学における基礎的知識を身に付けている。
(3) 心理学及び精神保健福祉学に基づく対人援助の方法に関する知識を身に付けている。
【思考・判断】
(4) 自ら考え、設定した課題について、心理学及び精神保健福祉学の知識を活用し、現代社会が抱える諸問題への解決方法について考察できる。
【関心・意欲・態度】
(5) 心のケアや生活支援に関心を持ち、その実践に取り組む意欲を持っている。
(6) 自分自身の心のありかたを分析し、対人援助に役立てる意欲を持っている。
【技能・表現】
(7) 対人援助の総合的アプローチとしてのカウンセリングの素養を身に付け、地域住民が心豊かに暮らすことに貢献できる。
-
2
CURRICULUM POLICY
教育課程編成方針
本学科では、ディプロマ・ポリシーに掲げる目標を達成するため、以下の方針に基づき教育課程を編成します。
【教育内容】
(1) 心理学・精神保健福祉学の修得に向けた準備のため、基礎教育科目としては大学での学び方を身に付ける基礎教育セミナー、語学、情報機器操作、現代生活と諸関連領域を含めた教養科目を学んでいく。加えて発展科目としては他学科の専門的な科目を履修することにより、人を取り巻く様々な環境について理解を深め、心の支援の実践に活かすための学びを深めていく。
(2) 就業力養成科目においては、専門的知識を援用した自身のキャリア形成のための自己探究やコミュニケーションのスキルを学んでいく。
(3) 専門科目においては、心理学に関するものとして、公認心理師国家試験受験資格を取得するためのカリキュラムを含む基礎から応用にいたる心理学の幅広い分野における講義・演習科目により、心についての理解を深めるとともに、「心の支援」に携わるためのカウンセリングの知識とスキルを修得していく。精神保健福祉学に関するものとしては、精神保健福祉士国家試験受験資格を取得するためのカリキュラムを通して、「生活と人との関係への支援」のための基礎的知識と実践に結び付けるための体験的知識を修得していく。
(4) 3年次以降では、専門演習において本学科で修得した知識と能力を応用し、研究的思考により発展させ、卒業研究において専門的な学びの総括を行う。
【教育方法】
(1) 1年次よりゼミ担任制をとり、学生の学びの状況を適切に把握し、よりよい学修状況へと導くための指導を行っている。
(2) 主体的な学びを促進するため、様々な形態のアクティブ・ラーニングを導入している。
(3) 専門性を高めるために、基礎的理論の理解に基づいた上で心の探究に関する研究方法や、心の支援を実践するための方法について理解を深めるための演習的な講義を展開している。
(4) 学内外における実習により、心の支援に携わるための実践力を身に付ける。
(5) 専門演習・卒業研究においては各自のテーマに基づき主体的に文献検索を行い、得られた成果のプレゼンテーションとディスカッションを経て研究としてまとめていく。
【教育評価】
(1) 各科目において設定された到達目標の達成については、設定された方法に基づき、講義中の発言内容やレポートの状況、試験の成績等を総合的に判断し評価を行う。
(2) 最終年次には、大学での学びを総括する取り組みである卒業研究において研究成果を提出物ならびに口頭発表によって示す。
-
3
ADMISSION POLICY
入学者受け入れ方針
本学科では、以下に示す資質・能力等を身に付けた者を受け入れます。
(1) 高等学校の教育課程を修了し、高等学校卒業に相当する学力を身に付けている。
(2) 高等学校までの履修内容を通じて、聞く・話す・読む・書くというコミュニケーション能力の基礎的な内容を身に付けている。
(3) 心理学や精神保健福祉学に関する社会的な諸問題について、自ら得た知識・情報に基づいて論理的に思考し、それを説明することができる。
(4) 入学後の修学に必要とされる、コミュニケーション力、及び、主体性をもって学ぶ姿勢を持っている。
(5) 自分自身の心、自分を取り巻く他者の心、そして人と人とのかかわり合いについて理解を深める意欲を持っている。
(6) 心理学・精神保健福祉学の専門知識に基づき、人間理解と対人援助に力を注ぐための実践能力を身に付ける意欲を持っている。
カリキュラムマップ

PDFはこちら
取得できる免許状・資格
| 免許状・資格 |
| 公認心理師国家試験受験資格 ※1 |
| 精神保健福祉士国家試験受験資格 ※2 |
| 認定心理士 |
| 福祉心理士 |
| 社会福祉主事任用資格 |
| 社会教育主事任用資格(社会教育士) |
| 児童福祉司任用資格 |
| 児童指導員任用資格 |
| 臨床心理士 ※3 |
※1 大学で所定の単位を修得後に、大学院で必要な科目を修了する必要があります。または、大学での所定の単位を修得後に特定の施設で特定の期間従事する必要があります。
※2 精神保健福祉士受験資格取得のための演習・実習科目の履修希望人数が25名を超えた場合は、選抜を行います。
※3 臨床心理士受験資格を得るには指定大学院の修了が必要です。本学大学院は臨床心理士受験のための第一種指定大学院で、修士課程修了後に実務経験なしで受験資格を得られます。
就職について
※心理カウンセリング学科では教育職員免許状の取得はできません。
※2022年度については2023年5月1日現在、2023年度については2024年5月1日現在、
2024年度については2025年3月31日現在のデータを掲載しています。
また、就職率につきましては、就職者数÷就職希望者数で算出しています。詳細はこちらをご確認ください。
心理カウンセリング学科の最新情報一覧を見る